「………すき」 君が、囁く。 透けるように白い肌を、ほんのりと染めて。 「私も、好きです………」 君が、呟く。 幾度となく紡がれる恋の歌は、揺らめく眼差しと共に。 君への憎悪を、掻き立てる。 偽恋歌 -girenka- 時折、その白く細いたおやかな首を、へし折ってやりたい衝動に駆られる。 共に時空を超えてやってきた友人達と、笑顔で戯れる少女の姿を。 友雅は、柔らかな微笑を眦に貼り付けたまま見つめていた。 龍神の神子と年若い八葉らが揃えば、静寂に包まれていたはずの土御門邸も、さんざめく笑い声に包まれる。 贅をこらしてはいるが、友雅にとっては面白味に欠ける単色のような邸内は、彼らがいるだけで鮮やかな色に染まり。 最初は呆れて遠巻きにしていた女房どもも、今ではおかしそうに、そして微笑ましげな笑みを浮かべて少年達のじゃれ合いを眺めていた。 京に蔓延る鬼の妄執。 怨霊の気配。 死への恐怖。 加速する飢餓や貧困。 癒えることのない怪我や病。 泰明や永泉らの結界によって、下手をすれば内裏より安全とも言えるこの土御門にあっても、それらへの恐怖は人々の心内を蝕んでいたというのに。 温かい光を身に纏い、許しを与え、そして全てを慈しむ少女は、意図せず溢れ出た輝く笑顔でもって彼らを癒す。さすれば、惹き付けられずにはいられないのだ。 ──この自分のように。 脇息に頬杖をつき、微笑ましげな表情を崩すことのない友雅は、心中で吹き荒れる狂風を認識していた。 「やだあ!天真くんのイジワル!!」 彼女が弾けるように笑えば、この胸は引き絞られるように痛み。 「あかねっ!…まったく、しょうがねぇなあ…」 激しい瞳を緩めた少年が、手を伸ばして春色の髪をくしゃりとまぜれば、鳩尾に重い物が落ち。 「それって、図書館にあったやつでしょう?ホント、好きだよねぇ〜あかねちゃんっ」 柔らかな気配を一層温かくした少年がうっとりと零せば、吐き気にも似た激情が奔る。 なぜ、こんな幼い少女に捕らわれてしまったのか。 どれほど思考の海を漂おうと、その答えはいまだ謎のままだ。 生涯、解き明かされることなど無いのかもしれない。 それでも、構わなかった。 これと言った執着心も、確たる情熱も、生きることの意味さえ持たなかった自分。 それが今まさに、この少女に執着している。 いや、執着などと軽々しく言えるほどのモノではなかった。 ──嗤えるではないか。 屍のように、濁った双眸を持ち。 何に対しても無感動、無関心だった男。 それが今では、年端もいかない少女の一挙手一投足に激しく浮沈し、そして狂おしいほどの嫉妬に身を焦がしているなど。 息もできやしない。 吐き出した呼気ですら、少女を取り囲む男共を呪う、まじないとなってしまいそうだった。 逃がしはしない。 逃がしはしないのだよ────あかね… 思わずくつり、と漏れ出た嗤い。 その気配を感じたのか、他の八葉らと戯れていたあかねが、ふと友雅を視界に納めた。 僅かに歪められた頬。 怯えたように彷徨う眼差し。 「それで、微笑んだつもりかい?」 小さく、小さく零れ落ちた呟きは、誰の耳にも届かない。 そう、それでいい。 彼女の本心を。そして自分の心の裡を。誰に知らしめるつもりもなかった。 むしろ、表層だけの睦まじさが、真実となるまでは決して誰にも覚られてはならない。 本当に、莫迦な子だ。 愚かで、卑怯で、傲慢で、強欲で、そして──愛しい。 友雅は脇息に凭れ微笑を浮かべたまま、蝙蝠を開いてひとさし扇いだ。 己の裡で暴れ狂う、愛憎を宥めるように。 「──おいで、神子殿」 うっとりと眼差しを和らげて告げれば、ピクリと小さく揺れた肩。 おずおずと探るように揺らめく眼差し。 そして、嬉しげに染まる頬。 「ともまささん…?」 媚びるように、けれど優しく撫でるような声に、浮遊感が沸き起こる。 彼女だけではない。 自分でさえ、何と愚かで莫迦な男だろうか。 そして、彼女を呼ぶ声に反応し、不快げに鼻白む彼らも。 皆、救いようのない愚か者だ。 「友雅さん?」 窺うような上目遣いで近付いてくる少女の手を取り、強引に膝へと導く。 驚き、羞恥に染まった頬。それでも、嬉しげに緩んだ口元。 くんっ、と小さく握られた直衣の胸元が、熱く、熱く疼いた。 「神子殿、そろそろ…君に焦がれる私の相手もしておくれ?」 耳朶を食むようにして甘く囁けば、眩暈に倒れるように顔を伏せ、首筋を真っ赤に染める。 「と、友雅さん、なにを…っ」 照れながらも戸惑うその様に、酷く嗜虐心があおられた。 「おい、友雅!あかねが嫌がってんだろ!」 「ほう?天真は神子殿のお心がわかるのかい?それはまた、由々しき事態だねぇ」 「ああん?アレだろ。友雅は、俺らとあかねが仲が良いからって、嫉妬してんだろ?」 憐れむような、優越感を滲ませた瞳の色に、怒りが込み上げる。 それを表に出すような、愚行はおかしたくない。これ以上の愚か者に成り果てるのは御免だった。 しかし、堪えれば堪えるほど。彼女の温もりを、腕に、胸に、心に感じるほど。制御できない焦燥と、憤怒に支配されていく。 友雅はつい、と腕の中のあかねに視線を落とす。 ピクリと震えた薄い身体。視界の端には、険悪になっていく空気に戸惑うような素振りを見せる詩紋が、必死に天真を宥めていた。 ──莫迦な子だ。 再び心の裡で呟いた。 天真に向かって嫣然と微笑んで見せ、腕に囲った少女の髪に鼻先を埋める。 朝から散策に出ていたあかねの髪は、汗に混じった埃と、ひなたの匂いがした。 「──嫉妬だって?」 クスクスと零れ落ちる笑いは、音に反して辺りの気配を凄まじい勢いで鋭くさせる。 食ってかかる少年の喉が、大きく上下した。 「当然だろう?神子殿は、ただひとりの私の恋人。他の男と囀り合っているのを見て、怒りを感じずにいられるほど、私は優しい男ではないのだよ」 見せつけるように口づけた頭部が、フルフルと震えている。 唖然とした天真の顔。 表情を隠しきれず、憮然と睨み付ける詩紋の顔。 他の八葉たちも、皆一様にして戸惑いを浮かべていた。 「──恋人、というのは…神子殿を入内させようという輩への、『目眩まし』では無かったのですか?」 苦虫を噛みつぶしたような鷹通の声は、決して否定はさせまいとする、強い意志が宿っていた。 彼の言うとおり、友雅とあかねは、『偽りの恋人』であった。しかしそれは、過去の話だ。 どれほど神子の存在を隠したところで、人の口に戸は立てられない。彼女が土御門に降り立って間もなく、その存在を知った貴族どもが、龍神の神子を怨霊や鬼に損なわれては龍神の加護が受けられなくなると恐れ、あかねを怨霊や鬼全ての穢れから隔離し、斎宮として伊勢へ送るよう画策を始めていた。 それと同時に、今上帝の元に神子を入内させ、何としても皇子を産ませようという輩までが出始め、宮中は混乱を極めていた。 そんな折、当の帝が、神子に会いたいなどと言い出したのだ。会って、京を守ってくれる感謝を伝えたいなどと言ってはいても、その本心はあかねを天上へ連れ去ろうとしているのだと思った。 その時の恐慌は、誰にも理解されることはないだろう。 密かに清涼殿を訪れた友雅は自分を兄のように慕い、そして何事においても友雅を尊重しようとする帝に、自尊心も何もかもをなげうち、伏して願い出た。 初めて心から愛しいと想った人を、どうか取り上げないで欲しい──と。 そうすることが、自分の願いを最も叶えられる手段であると、計算してのことだった。 頼もしく思いながらも、友雅の平素を案じていた帝は、難なくその願いを聞き入れ。 真から望んだ恋人を手放すことならぬ、と激励までして見せた。 諸々の山積した問題を知り、入内という御意を得なければならないのだと思い込んでいた土御門は、通夜のように静まりかえり。八葉はどのようにして神子を京から逃すかという算段に追われていたが、友雅が持ち帰った帝の言葉を聞くや、歓喜に沸き上がったものだ。 それから、あかねと友雅は、対外的には『恋人』として振る舞うようになった。 そして僅か数日後、彼女は友雅に心の裡を打ち明けた。 「おや、話していなかったかな。私がお慕いしているように、神子殿も私を好きだと言ってくれてね」 『友雅さんが、好き、です。…偽りじゃなくて、本当の恋が、友雅さんと、したい、です』 歓喜だった。 頬を染め、拙い言葉で語られるそれは、まさしく友雅の息の根を止める程の幸福を与えた。 緊張によって握りしめられた小さな掌。 伏せたまま、頼りなげに泳ぐ眼差し。 怯えたように肩を竦め、背を丸めて。 ささやかに震えたその恋の歌は、友雅の想いを暴発させた。 もう決して離しはしない。 何があろうと、離れはしない。 たとえどのような苦難があろうとも。 たとえ、どれほどの妨害に晒されようとも。 必ず、彼女をこの手で幸せにしてみせる── 「神子殿。──あかね…」 ようやくふたりきりとなった房室の中。 友雅は、膝に乗せて抱きしめた小さな身体を、慰撫するように撫でた。 ひくり、と震える肩に構うことなく、逃がさないとばかりに腕の戒めを強くする。 「…、友雅さ……ン…」 春風のような吐息。 甘く震える唇。 そっと触れあわせた桜色のそれは、温かく、柔らかで。 胃の腑を握りつぶされるような感覚を、そろりと息を吐き出すことでやり過ごす。 ゆるゆると舐め上げた口角が緩んで、小さな歯が舌先を刺激した。 舌根までもねじ込んで薄い舌の裏側を辿り、蜜腺をねぶれば、ドッと溢れ出た唾液が互いの間を渡る。 「──は、ン………ぅむっ……」 飲み下しきれなかった雫が零れ、白く小さな顎先へと伝っていくのを舌で追いかけながら、友雅は沸き上がる常の想いに捕らわれていた。 この瞬間に、息の根を止めてやれたら…どれだけ満たされるだろうか。 そっと触れた、細い首筋。 心の奥底から滲み出るその誘惑を振り切るように、脈打つ頸動脈を辿って、そして小さな胸元を探る。 瞬間。 あかねは電撃に打たれたように、身を竦めた。 はっし、と掴まれた掌。戸惑いと恐怖が浮かぶ双眸。 「嗚呼…」と胸の裡が絶望感に満たされる。 「あ、あの…えっと………ね、?」 与えられた接吻に瞳を潤ませ、むしろ友雅の全てを吸い付くさんとしていたくせに。 いざ、その先に進もうとすると、愛らしい上目遣いで拒絶する。 どれほど彼女を想い、どれほどその存在に焦がれ、どれだけの独占欲と征服欲を抱えているか。多少なりとも気づかぬはずなど、ないというのに。 彼女は、友雅に全てを与えようとはしない。 ──決して。 重く垂れ込める闇を振り払うように、そっと苦笑を零し、それ以上の侵略を止める。 諸手を挙げて降参の態を示してやると、彼女はあからさまにホッとしたように肩の力を抜いた。 「──わかってる。全ての問題が、片付いてから。だろう?」 「…はい…。もしかしたら、関係なんて…無いのかもしれないけど…」 「君の不安も、きちんとわかっているつもりだから、大丈夫だよ。神子や巫女などといったものは、清らかでなければならない、と。そう相場は決まっているからね」 「誰かにそう、言われたわけじゃないけど…やっぱり、万が一のことも、考えないと──」 頼りなげに下げられた眉。ほんの少しだけ身体を離して見遣れば、小刻みに震える両の掌は、友雅の直衣の裾を固く握りしめていた。 緩やかに微笑をはいて、乱れかけた春色の髪を梳いてやると、そっとそっと、細い溜息が零れていくのを感じる。 「待たせちゃって、ごめんなさい。でも、その、イヤってわけじゃなくて──その…」 「君も、私を求めてくれているのだよね?だから、いつか──近い将来、君を抱いても…いいかな?」 恥ずかしげに染まった耳朶や首筋。 彷徨った眼差しは、やがて友雅の瞳をやんわりと捕らえ。 そして── 「──はいっ!」 その場にそぐわない、朗らかな返事が。 憎らしい唇から、零れ落ちた。 嘘つき |
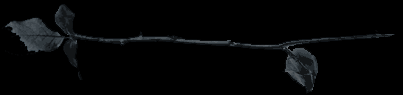
| さくらのさざめき / 麻桜 様 |