月明かりが照らし出す簀の子縁で、友雅は高欄に頭を預けるようにして座り込んでいた。 整えられた庭に棲む虫の声さえ、聞こえてはこない。 土御門殿は薄気味悪いほど静まりかえり、孤独感はいやおうにも増していく。 あらかた呑み尽くされて軽くなった酒器を、割り砕いてやりたい衝動を抑えつつ、友雅は深く溜息を落とした。 日没と同時に、あかねの寝所である西の対屋から追い出され、立ち入るべからずと固く言い渡されてから数刻。もう日が変わった頃だろうか。 暗闇に浮かぶ釣灯籠の火が、風に揺られて僅かに音を立てた。 あかね── 声に出さず呟くと、ただそれだけで胸が鷲掴みにされたように痛む。 幼い小娘のような反応に、思わず苦笑が漏れた。 もうすでに深く眠りについているだろう彼女は、今頃自分の夢を見てくれているだろうか。 それとも、彼らの故郷へと思いを馳せているのだろうか。 いつか帰ってしまうだろう場所。 何でも良い。そこに、彼女の隣に、自分の居場所があるのなら。それで── 「こんな夜更けに、何かあったのかい?──詩紋?」 ギ、と小さく渡殿を軋ませて現れた少年は、夜着の単の肩に狩衣を羽織っただけの格好で、所在なさげに立っていた。 放り投げるようにして懸盆に落とした杯が、不快な音を立てながら跳ね上がる。 「…友雅さんこそ、どうしたんですか?もう、真夜中ですよ?」 柔らかな微笑みを浮かべ、心配そうな素振りで側までやってくる。衣擦れがやけに響いて、いやに耳に触った。 「──眠れなくてね。だが、酒ももう尽きてしまった…」 吐息混じりにひっそりと零せば、コトリと首を傾げた少年の髪が、月明かりに映えて美しく輝く。 ボクもなんです、と苦笑混じりに呟く声は、少しだけ掠れていた。 「何か、あったんですか?随分…塞いでいるように見えますけど」 「──塞いでる?そんな風に見えるかい?」 「ええ、疲れてるというか、落ち込んでいるというか…」 心底案じていると言いたげな気配に、クツクツと嗤いが込み上げてくる。 嗚呼、本当に莫迦な子── 「──友雅さん?」 訝しげな声。眉の下がった、困惑顔。突然の笑いが理解できないのか、情けなさそうな雰囲気に、反吐が出る。 「幼げな顔をして、随分とやり手のようだね。詩紋?」 「…え、えっと?何のことですか?」 「花のような、良い香りがするね。涼やかで、凛としていて。そしてほんの少し、甘い。君には少し…似合わないようだけど」 「え、そんな匂いしますか?どこで移っちゃったんだろう…?」 鼻を鳴らして袖や襟元を嗅ぐ様は、まるで子供だ。 「土御門で、この香りを身につけるのは、ただひとり。君も隅に置けないね、いつの間にそんな仲になっていたんだい?」 「そんな仲って…」 心底わからないというような顔を、ちょいちょいと蝙蝠で呼ぶ。戸惑いながらも近付いてきた単を掴み、ぐ、と少年の固い首筋に鼻先を近づけた。 「肌にまで、移り香を染みこませるような──そんな仲のことだよ」 先程、詩紋がやって見せたように鼻を鳴らして匂いを嗅げば、そこからは詩紋の香りと、僅かながら菫のような薫香がする。この香は以前友雅が、ある女房に贈ったものだった。 ピクリと肩を揺らした詩紋は、警戒したような気配を帯び始める。 「ねえ、詩紋」 掴んでいた襟元から、突き放すように手を引く。 空になった銚子をゆらりと揺らしながら、襟を正すでなく立ち尽くす少年を見上げた。 少しずつ、引き絞られていく気配。 口元にはいた笑みとは反して、まん丸と幼げに開かれていた双眸が、『男』の鋭さを増していった。 「君に感謝しなくてはならないね」 カツン、と杯にぶつかった銚子が高らかに鳴った。 普段は陽の光のように穏やかで優しく、温かい眼差しが、剥き身の刃のように冷徹な光を帯びる。 それと同時に、緩やかに引かれていた口角が、吊り上がるようにして酷薄な笑みを浮かべた。 「なんの、ことです?」 ボクにはわからないなぁ。 囁かれた言葉は、嘲るような笑いを含み。 「感謝、って──突然、どうしたんですか?」 クスクスという心底おかしそうに転がる笑い声が、臓腑を掴み上げ、息苦しくさせる。 唐突な変貌を遂げる少年は、不遜に腕を組みながら柱に身をもたせかけた。 「────神子殿を、私に譲ってくれたろう?」 うっそりと微笑み返せば、ぐ、と引き絞られる双眸。 そこに平素の可愛らしい様子は微塵もない。 「おかげで私は、この世の春を満喫しているよ」 こちらを見下ろす瞳に変化はない。しかし、組んでいた腕に突き立てるようにした指先が、ギリギリと食い込んでいく様が見えた。 「君が、彼女に入れ知恵したのだろう?」 少年に言葉はない。 気づかれていないとでも、思っていたのか。 だとしたら、考えていたよりも、ずっと愚かだ。 「私に、偽りの恋の歌を、と──」 風がざわめく。 雷鳴が轟きそうな不穏な気配に、怯えるかのように庭の木々が枝を打った。 細く、深く吐き出される溜息。 鬼などでは相手にならないだろう程の、冷徹な微笑。 月明かりを反射した金の髪が、白い肌が、ぼんやりと闇の中に浮かんでいる。 「やだなぁ、何のことですか?」 「もう、今さらとぼけなくても良いのだよ、詩紋。君が、彼女のためを思ってのことだと、わかっているのだから」 「ボクが?あかねちゃんのために?友雅さんに、何をしたと?」 「私が神子殿に恋情を抱いているのを知っていて、彼女が貴族どもの手に堕ちぬよう、私に守らせようとした」 「それは、アナタが自分で決めて、自分で手配してきたことじゃないですか?」 「そう、そして君は──それを利用した。神子殿に私が恋しいのだと偽りを告げさせ、決して他の者どもの手が及ばぬように、私に守らせることにした」 それに気づかぬ自分ではない。 当初は、危急の事態を回避するため、己の恋情を盾に帝を操った。 俄に生じた龍神の神子 入内の論議を打ち棄て、盛り上がる斎宮論を一笑に付し。 神子への手出し無用の確約を得た。 条件は、友雅のさらなる忠誠。そして、龍神の神子を生涯、京に留め、守護を得ること。 彼女の心が自分にないことなど、とうに知っていた。それでも、その時は恋情を訴え、恋人を取り上げないでくれと懇願してみせることが、最も確実な方法だったのだと今も信じている。 「私が彼女を、傷つけることなど出来ないと知っていて。貴族どもへの牽制に、私を使った」 神子を──あかねを、他の男になどくれてやるつもりはない。 自分を置いて、故郷に帰るなど許せるはずもない。 笑顔も、優しさも、涙も、怒りも、全て。彼女の全てが、欲しかった。 頑是無い幼子のように。 ただただ、自分を見て、そしてその傍らに置いて欲しかった。 「何より、彼女が私を心から信じ、愛することなどないと、確信していたのだろう?」 だから、そうと知れぬように。 真綿で首を絞めるように。 見えぬ糸で、絡め取るように。 「恋情を募らせた私が、彼女を傷つけることのないよう、泰明殿まで巻き込んで」 少しずつ、少しずつ彼女を浸食していった。 最初は僅かな接触を。裏のない微笑と、正直な言葉。 ほんの少し、大胆に。唇を寄せて、そっとそっと、心に触れるように。 時に慰め。時に叱咤し。そして、包み込むように抱きしめた。 「『神子は神聖でなければならぬ』 『穢れを知らず、清らかでなければならぬ』だったかな?」 そして彼女は今、この手に堕ちかけている。 誠実に、真摯に、ただひたすら強く想う心だけを晒し。憎らしいと、嘘つきだと詰ってしまいたい、恨みの念を封じてきた。 「私は、彼女に触れることも叶わず。ただただ、愛しいのだと想いを伝え続けるしかない、愚かな男に成り下がった」 もう、決して連れ戻させはしない。 少年も、彼女を恋うる気持ちを押し殺し、それでも友雅にその身を預けたのだろう。 この地には、この地の通則がある。 それらに翻弄されぬよう。彼女を失うことのないよう。損なうことのないよう。 苦しみ藻掻きながらも、友雅に守らせる方法を選んだ。 「彼女は伺いを立てるように、君のことを盗み見ることが多かった。だから、君が糸を引いているのだろうと思ったのだが──間違いだったかな?」 ならば、守りきってみせる。 彼女を失うことなど、出来ないのだから。 「────利用できるモノを利用して、何が悪いんですか?」 大人になりきれない、高い声。 じっと友雅を見据える面からは、もはや笑みの残滓など掻き消えていた。 底冷えするような眼差しは、嫉妬と嫌悪に鈍く光っている。 「ボクらは、強引にココへと連れてこられた。何もわからないのに、何の関係もないのに、命を掛けて京を救えと、理不尽に迫られた。身勝手なその命令に、従う義務はない。けれど、従わなければその場で命は尽きる」 彼の言葉は、もっともなことだった。 自分たちが彼らに強いたのは、生贄となれ、そういうことだ。 「ただでさえ反吐が出る思いなのに、アナタ達は、ボクらからアノヒトを奪おうとしたじゃないですか」 詩紋の全身から、憎悪にも似た念が沸き上がってた。 許すことなどしない。決して、奪われるつもりもない。 そう言っているようで、友雅もみずからの掌を握りしめた。 「この地の最高権力者に一目置かれるアナタは、使える。そう判断してさし上げたんだから、感謝して欲しいくらいですよ、友雅さん?」 無表情の幼い顔が、まるで般若のように見えた。 「アナタは、恋しいあかねちゃんの側にいることができる。良かったじゃないですか。何か問題でも?」 「なぜ、私なんだ…。偽るのなら、永泉様でも、鷹通でも良かったはずだ。私が彼女の嘘に、気づかないとでも思ったかい?」 絞り出すように呟いた言葉に、少年は侮蔑の笑いを零す。 常の彼からは想像も出来ないようなその様に、背中がざわめいた。 「下手に純粋で、免疫のない人は困るんですよ。堪え性がなくて、あかねちゃんに襲いかかられでもしたら、たまったモンじゃないんですよね」 「それは、私でも同じ事だろう?」 「アナタは、世捨て人みたいなことを言っているけど…その実、山のように自尊心が高くて、自分に自信を持っている。無理強いすることも、壊してしまうことも、良しとはしないでしょう?あかねちゃんが欲しいなら、手練手管は駆使しても、必ず正攻法で攻めてくる。そう思ったんですよ」 一時の慰めが欲しいわけではない。 彼女の全てが、その心の奥の奥までもを手に入れたいと思っていることを、彼は見抜いていたというのか。 詩紋はあからさまな威嚇の意を乗せた眼差しを、友雅に叩きつけた。 「ボクの見立ては、間違っていなかったでしょう?アナタは、あかねちゃんを傷つけられない。優しくして、包み込んで、時に弱いところをもさらけ出して、アノヒトの憐れを買おうと必死のアナタに。あかねちゃんを泣かせることなんか、できない。違いますか?」 ──思わず、笑いがこみ上げてきた。 こんな子供に見抜かれ、操られようとしていた。 だが、他人に晒したことのない心の裡を暴かれて、並べ立てられたことで、吹っ切れたような気もする。 身も知らぬ地に放り出され、周囲の何もかもが恐ろしく感じていただろう彼女が、無謀とも言える計画を受け入れ実行に移した。 それは、この少年がどれほど信頼されているか、ということを露呈しているように思えて、目も眩む嫉妬と憤りに苛まれていたのだ。 だが、これほどまでに自分でさえ、さほど意識していなかった事まで言い当てた少年の心もまた、近しい闇を飼っているのだと知る。 「──君は聡い子だね。まったく、敬意に値するよ」 零れ落ちる笑い。肩が震え、止まらない。 苛立つ気配が、僅かな衣擦れと共に耳に届く。 「だが、君は、喧嘩を売る相手を間違えたようだ」 鋭利さを増すように、細められる双眸。 自らの腕を傷つけるように、溢れ出す憤りを押し殺すように、指先が白く単を握る。 「──君が折角譲ってくれたのだから。大切に、大切に慈しむよ」 せっかく、煩わしい八葉達にも、関係を知らしめたのだから。 彼の言からすれば、利用できるモノは利用して、悪いことはないようだから。 「手加減なく、全力でもって、今以上に惚れさせてみせよう」 不快げに、訝しげに寄せられた双眉。 なにを、と模られた唇が、小さく戦慄く様が、心地良く感じられた。 「私は貪欲なものでね。甘い唇を与えられた位では、満足は出来ないのだよ」 僅かに驚きを乗せた瞳が、跳ね上がった眉尻が、少年の計画が破綻しかけていることを示している。 絶望を与えてあげよう。 彼女の心が不在であると、疑い始めた時の、自分のように。 零れ落ちる恋の歌が、偽りであったと確信した、瞬間のように。 「今日の彼女も、明日の彼女も、明後日も、明明後日も…未来永劫、一欠片も余すことなく彼女を愛したい。そして、私の存在を刻みつけたい。それも、遠い未来の話しではないさ」 ザアン、ザァン、と風が吹く。 長い髪を嬲り上げるその風に、想いを乗せて彼女に届けたい。 「──あかね は、もう、私を愛し始めているのだから──」 闇に沈む簾の向こうに射し込む、一条の月明かり。 そこに翻った春色の髪は、白々と輝いている。 そして、にいやりと引き上げられた口元からは、楽しげな笑い声が微かに響いて── 誰に気づかれることなく、夜に消えていった。 -終- |
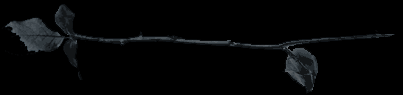
|
|||
| さくらのさざめき / 麻桜 様 | |||