ずるいのよね、アンタって いつもニコニコ良い子ぶって そりゃ皆、アンタのことちやほやするわよ アンタは「たまたま」神様に選ばれてすっごい力を手に入れて 周りの連中も「特別な」アンタにアタリの良いことばっか言われてさ そりゃあアンタのこと大事にするわよねぇ 絶対悪口なんか言わないんだもん あら、なぁに? ふぅん、そんなに自信あるんだ? じゃあ────── 試してみようか? 天探女(あまのさぐめ) ねっとりとまとわりつくような、夜の闇の底で。 微かな声と吐息が漏れるごとに、淫猥な気配が辺りに撒き散らされる。 「んん・・・・・やっ、そこ・・・・も・・・うっ・・・・ふぅ、んっ・・・!」 「だめだよ、神子殿・・・そんな風に声を堪えては。君が甘く蕩けていく声を聞かせておくれ?」 友雅は組み敷いた白く華奢な肩にかりっと歯を立てる。 あかねは白い喉を押し出すように身を仰け反らせた。 快感の叫びがこぼれそうになるのを、はだけられ腕に引っかかっているだけになった単を ぐっと握りしめてなんとか堪える。 「ねぇ・・・神子殿?」 「やっ・・・・だめ・・・です・・・・。だって、皆に聞こえちゃうっ・・・!」 あかねが元いた世界と異なり、『壁』のほとんどないこの世界の建物構造。 局の奥まった処に設けられた御帳台の周りにさらに何重にも几帳を立て、決して外からは 見えないようにしてあっても、車の騒音も何もないこの京では、その気になって 耳を澄ませば自分の恥ずかしい声が聞こえてしまうのではないか────── 。 散々友雅に翻弄され、いつの間にか自分も熱い快楽を求めて自然に動けるように なってしまっても、あかねはまだまだ恥ずかしいと思う心をなくせない。 「大丈夫だよ。君がそうやって恥ずかしがるからね、私が来ている時はこの西の対には 人を近寄らせないようにしてもらっているから。もちろん、警護の頼久もいない。 私と君の、2人だけだよ。だから・・・・・・ね?」 つつ・・・・と形良い指で脇を撫で上げられ、あかねの体がびくん!と跳ねる。 「そ・・・・それって、つまり、友雅さんとここでこうしてるってこと・・・みんなに知られてるって ことじゃないですかっ!」 声を聞かれるのも恥ずかしいが、今こういうことをしているということを知られているのだって 十分気恥ずかしい。 友雅は軽く首を傾げる。 「当たり前だろう?婚儀こそまだだけれど、私と君が恋人同士なのは皆知っているのだもの。 私たちがこうして仲睦まじいことを喜んでくれていると思うけれど?」 至極当然のことのようにいう年上の恋人に、あかねは真っ赤になったまま口がきけない。 何も分からないまま異世界であるこの『京』へやって来て、『龍神の神子』と呼ばれて。 否応なく鬼との戦いに巻き込まれた時はいったい何の因果で、と幾度も己の不運を嘆きはしたが、なんとか戦いを終結させ、自分を守ってくれた八葉の一人である友雅と想い想われる仲となった今ではこの運命に感謝もしている。 まだまだあちこちに残った怨霊を鎮めるため、そして生まれ育った世界とはまるで違う この世界のことを学ぶため。すぐにも正室として自分の屋敷に来て欲しいという友雅を 何とか押し止め、あかねはすでに自宅と言って良いほど慣れた、ここ土御門邸に落ち着いている。 いつの間にかあかねをただ一つの情熱と思い定めていた友雅は、あかねもまた自分を想って くれていると・・・その想いが、幼い憧れから男女の愛に育つまでじりじりと待っていたのだ・・・・・ 分かるとすぐに2人の仲を公言した。 それはもちろん周りにひしめくライバル達を出し抜き牽制するためではあったのだが、何より 友雅自身があかねと離れることなど耐えられなかったから。だからすぐにも四条の自分の屋敷へ浚ってしまいたいところなのに。 この京に残るからには裳着をすませ、正式に左大臣家の養女として嫁がせたいと主張する 藤姫はともかく、あかねにまで『ちゃんと奥さんらしいことが出来るようになってから』嫁ぎたいなどと言われては、無理強いも出来ない。して欲しい『奥方らしいこと』など友雅から見れば 一つしかないのだが、それを言ってはまた藤姫の逆鱗に触れる。 これ以上2人の仲を邪魔されてはたまらないので友雅としてはかなり譲歩して、しばらく恋人として『通う』ことで我慢しているのだ。 本音を言えばこっそり忍ぶどころか、行列を仕立てて堂々と通い、あかねは自分のものなのだと京中に触れ回りたいほどなのに。 何故隠したいのか心底理解できない、という顔の友雅にあかねはますます顔を赤くする。 同じ年頃の少女に比べても晩生であるあかねには、『好き合ったならエッチは当然』などとは 開き直れないのだ。 「や・・・やっぱ、恥ずかしい・・・です・・。」 俯いてしまうあかねを内心ひどく可愛いと思いながら、捻くれた男はわざと声を落とす。 「神子殿は・・・私とこうして睦み合うことが、恥ずかしいの?君と私は互いに求め合っていると 思っていたけれど・・・優しい君は、天女を求める哀れな地上人に同情してその御身を 与えてくださっていただけなのかい?もしそうなら・・・・申し訳ないことをしたね・・・。」 急に体が軽くなる。すっと身を引いてしまった友雅にあかねは慌てて顔を上げた。 どこからか忍び込んでくる微かな月明かりに鍛え上げられた美しい筋肉が浮かび上がった。 いつものあかねなら恥ずかしくて目を逸らしつつ、でもやっぱり見たい・・・と挙動不審になって しまうのだが、今はそれどころではない。 「え?ち、違いますっ!私、ホントに友雅さんが好きです!同情なんかじゃありません!」 「無理なさらなくてもよいのだよ・・・。君は、こういうことをしたくないのだろう?」 こういうこと、が何を指すのかなんて、今更野暮は言わない。 体を起こし項垂れたまま、ゆっくりと脱ぎ捨てた衣に手を伸ばす友雅。 あかねは慌てて肘を突いて身を起こす。 「そんなことありません!私、友雅さんと一緒にいられてすごく嬉しいんですから!」 「いやでは、ないの?」 「嫌じゃありません!そ、そりゃ・・・ちょっと恥ずかしいけど、でも友雅さんとす、『する』のが 嫌だなんてこと・・・・。」 段々尻つぼみになってしまうあかねに更に友雅は畳みかける。 「・・・私を欲しいと思ってくださってる?」 あかねはこれ以上は無理と言うほど赤くなって俯いてしまう。 だが小さく、それでもはっきりとあかねは頷いた。 見られないのを幸い、友雅の顔に蕩けそうな笑みが広がる。 「では、ね、神子殿。・・・君の口から、はっきりそう言っていただきたいのだけれど?」 「は・・・・?」 「私が欲しいと、ね?」 「ええーっ!む、無理です、そんなの・・・言えるわけ、ありませんっ!」 「そう?・・・やはり、神子殿は私に合わせてくださっていただけなのだね・・・本音では、 私のことなど望んでは下さっていないのだね・・?」 暗闇とうねる見事な黒髪で、俯いてしまった友雅の表情は見えない。 だがあかねはその声音から友雅がひどく傷ついたのだと思った。 ごくり、と息を飲み込む。 考えただけで顔から火が出そうだ。 だが、自分の命と引き替えにしても守りたいと思った友雅を。元の世界も両親も全てを 捨ててもそばにいたいと思った恋人を、がっかりさせたままにしておきたくない。 あかねは震える手をそっと伸ばして、友雅の髪に触れる。 指に一房絡めとり、引っ張らないよう、ぎゅっと握って。 絞り出すような小さな声が、闇をくぐって男に届く。 「・・・・友雅さんが・・・欲しいです・・・。」 途端に友雅の全身をゾクゾクする興奮が貫いた。 誰にも感じたことのない愛しさと欲望と、泣きたくなるほどの幸福感。 友雅は俯いたままのあかねをそっと抱き寄せ、再び褥に倒れ込む。 「御心のままに・・・・・神子殿・・・・・・・あかね・・・。」 ちゅ、ちゅと顔中に口づけの雨を降らせては、その唇を深く奪って。 再び蕩けそうになってしまうころ、なんとか残った理性の欠片をかき集めて、あかねは 友雅の頬を両手で包み込んだ。 「ずるいです、友雅さん。わざと私に言わせたでしょう?そうやって友雅さんばっかり、 意地悪して・・・。」 ちょっとふくれる頬に何度目かのキス。そのまま耳に熱い囁きを注ぎ込む。 「おや、では君も私に意地悪をしてみるかい?」 くちゅり、とたっぷり唾液の絡んだ舌を差し込まれ、あかねの体が震える。 「あ・・・ん・・。い、いいんですか・・・?」 「もちろん、私も全力で受けて立つけれど。そうだね早速、この閨での勝負と行こうか? さ、あかね。・・・・・意地悪しておくれ。」 そう言いながらも友雅の体はしっかりとあかねを押さえ込み、手はひっきりなしにその 柔らかな肢体を撫で回す。あかねが何か出来るような隙はない。 「えっ、ちょ、ちょっと待ってください!ここでなんて、急に言われても、そんな・・・ あ、ああ・・ん!」 「くすくす。ほら、どうしたの?私にどんな意地悪を仕掛けてくれるのだい? ねぇ、あかね・・・?」 もはやまともな返事をかせなくなっているあかねを思うままかき抱き、友雅は柔らかな 夜の底に沈んでいった。 ◇◇◇ 東の空が少しずつ青くなっていく。篝火の火はとうに燃え尽きて、残った薪の表面が 白く力尽きているのが見て取れるほどになっている。 もうすぐ武士団の若衆が交代に来るだろう。 頼久は油断なく辺りに気を配りながら、そっと肩の筋肉を解した。 彼が一生の主と心に決めた龍神の神子の眠りを守ることは彼の誇りだった。 最近はしばしばその仕事を奪われることが多かったが、昨夜は友雅は宿直で 来られなかったのだ。 朝の爽やかな空気を大きく吸い込み、頼久はふうっと息を吐き出した。 微かな衣擦れの音にさっと振り向く。 差し始めの朝日を受けて輝くばかりの少女が御簾を少し持ち上げて顔を覗かせていた。 珍しい。 あかねは基本的に朝が弱い。 昼間、京の街を散策したり怨霊を封印して廻っているのだから仕方がないが、 たいがい藤姫が起こしに来るまで出てくることはないのに(特に最近は別の理由でも 昼近くまで起きてこられないこともあるが・・・)。 「おはようございます、神子殿。今朝はお早いのですね。」 頼久は向き直り、一歩階に近づいて、慌てて顔を伏せた。 まだ起き抜けなのか、ぼんやりした顔付きのあかねは、薄い単一枚・・・下着同然の姿 だったのだ。 あかね達異世界の者にとってそれはあまり「下着」の感覚がないようで、あかね本人は しばしばその格好で歩き回って藤姫に悲鳴を挙げられていたし、詩紋や天真も気にした様子も なかった。だがさすがに最近は必ず一枚袿を羽織るようになっていたのに。 こほん、と咳払いをし口を開きかけた頼久に先んじて、あかねが口を開いた。 「─────── 頼久さん?」 その声があまりに近く、そして常のあかねらしくない艶めいた響きがあって、頼久は思わず 顔を上げた。 いつの間にかあかねは階の一番下まで降りてきており、少し手を伸ばせばその肩に手を 触れられそうだ。 いや、現実にあかねはそっと手を伸ばし、頼久の胸飾りにつつっ・・と指を添わせた。 「・・・神子殿・・・?」 「ねぇ、頼久さん。どうしてそんなに一生懸命私を・・・『龍神の神子』を守ろうとするの?」 ねっとりと囁きながら見上げてくるあかねの口元には彼女らしくない艶めいた笑みが 浮かんでいる。頼久は心臓がドクン、と跳ねるのを意識した。 「神子殿は・・・・私の主ですから。この身に代えてもお守りすると誓いました。」 「ふぅん・・・その身体、私に捧げてくれちゃうんだ?」 くすくす笑いながら、あかねの手は次第に大胆に頼久の胸を撫で回していく。 「み、神子殿?・・あの、何かあったのですか?」 「あら、どうして?」 あかねは素足のまま地面に降りるとさらに頼久に擦り寄っていく。 武器を持った盗賊団に囲まれても、どれほど強力な怨霊と対峙しても一歩も引かなかった 天の青龍は思わず後ずさる。 しかしあかねはその動きにぴったりと寄り添い前へ進み、楽しくて堪らないといった顔で さらに頼久を追いつめていく。 柔らかな若草の瞳は悪戯っぽく揺れている。 命も捧げる覚悟の主。その言葉に偽りなどないが、その裏に純粋な忠誠心とは少しだけ 色合いの違う想いがあるのもまた確か。 自分のような者がそのような想いを抱くのは分不相応と人知れず心の奥底に封じ込めて きたが、尊い齋姫はそんな心の奥まで見抜くのか。 鍛え上げられた胸にそっと添えられているだけの小さな手に抗えず、頼久はどんどん後ろに 下がる。コツ、と沓に硬いものが当たりそのまま自分の体が後ろへぐらりと倒れていくまで。 そこがあかねが庭を楽しめるようにと藤姫の心づくしで作られた池であることを 思いだした時には、彼の長身は見事に水の中に落ちていた。 ◇◇◇ 「神子、このような早朝からお邪魔いたしまして申し訳ございません。 ご機嫌はいかがでしょうか?」 朝餉の膳が下げられたころ、躾けの行き届いた左大臣家の女房に先導され、あかねの 局に顔を出したのは永泉だった。 京の街が鬼から開放され、八葉としての役目より本来の「御室の皇子」と呼ばれる 僧侶としての役目が多くなりがちになってはいたが、彼とていまだその掌に八葉の証の 宝珠を抱く八葉だ。龍神の神子を守る使命を怠る訳には行かない─────と自分に 言い聞かせ、あかねのご機嫌伺いに珍しい唐菓子を抱えて参上したところだ。 「ご無沙汰いたしまして申し訳ございません。しばらく法会が続きまして・・・・あの、 大僧正様より珍しいお菓子を頂いたのです。神子がお好みになるかと思いましたので・・・。」 そっと懐から、高価な綾織りにくるんだ菓子を差し出し、あかねの方へ押し出す。 いつものように、 『わ、美味しそう!良いんですか永泉さん?私、甘いもの大好きなんです、ありがとう!』 と、満面の笑みを浮かべてくれることを期待して。が。 「───── ご機嫌取りですか?」 常からはかけ離れた冷たい声に永泉は、え?と顔を上げる。 京の街に出掛けるいつもの水干と素足を晒すスカートという衣装。 だがいつもの彼女らしくなく円座にぴんと背筋を伸ばして座るあかねが斜めに永泉を 見下ろしている。その口の端が歪む。 「出家したっていっても、元々皇子様ですもんねー、私みたいな小娘にヘイコラ従ってなんか いられませんよねぇ?」 「神子?」 何を言われているのか理解できず、あかねの攻撃的な雰囲気に永泉は思わず腰を上げた。 「『お寺が忙しい』って良い口実ですよね?都合の悪い時はそう言って逃げ回ってればいいし、 そんな風に貧乏人には手のでないようなモノ持ってくれば、簡単にごまかせちゃうと思って るんでしょ?永泉さんってずっるーい。」 永泉の顔がさっと朱に染まる。確かに自分は逃げている、と思う時がよくある。 それがたまらなく恥ずかしくて情けなく、落ち込むこともしばしばだ。 だがいつものあかねならそんな永泉にも 『大丈夫ですよ、永泉さん!自分の行動が良くないって思うなら、ちょっとずつ変えていけば 良いんですから!』と笑って励ましてくれるのに。 自分のあまりのふがいなさに、さすがの神子も呆れてしまったのだろうか。 「も・・・申し訳・・・・。」 消え去ってしまいたいほど恥ずかしく、よろめくように廂から出ようとして、何かにぶつかった。 菊花の香り。 白と黒の印象的な狩衣。 その向こうには人数分の白湯を捧げ持った女房を従えた藤姫が立っていた。 「泰明殿っ・・・!」 今のあかねの言葉を聞かれてしまったろうか? 自分の未熟さを今更ながらあからさまにされたようで居たたまれない。 「し、失礼いたします。」 脇をすり抜け立ち去ろうとした永泉の肩を泰明の華奢な、しかし信じられないほど 力強い腕が引き留める。 「やす・・。」 「神子。何をしている。」 泰明は自分が留めている永泉を見てはいない。 その色違いの不思議な瞳は真っ直ぐに局の中央───────あかねに注がれている。 何の感情も映さないように見えるその顔が、微かな不快感を浮かべていることに 気がつく者は果たしてどのくらいいるだろう。 永泉の肩を離すと泰明は懐から呪符を取り出し、退魔の呪文を唱え始める。 「泰明殿?」 永泉は慌てて向きを変えた。なぜ、神子に向かって退魔呪を? 対してあかねは投げやりなため息をつくと両手を挙げて頭の後ろで組む。 「あ~あ、泰明さんってホント頭固いのね。それにすぐ力業? 自分がちょっと人にはない力があるからって、いい気になってるんじゃないの? ・・・・ああ、当然だっけ、『人』にない力があるの?」 あざけるような言葉に呪符が一瞬揺れる。 だが、詠唱に乱れはなく、呪符に力を込めつつ、泰明は一歩、局に足を踏み入れた。 「・・・・・・・・待ってください、泰明さん!」 泰明の声が止む。 永泉が局に目をやると、一転あかねが苦しそうに胸を押さえ、蹲っている。 だが、その目は真っ直ぐに泰明と永泉を見つめ、先ほどまでの冷たい嘲りの色は どこにもない。 「待って・・・・。お願い、少し待ってください・・・。」 「神子、どうされたのですか!」 「神子様!」 「近寄るな。」 あかねの突然の変化に、永泉と藤姫が思わず駆け寄ろうとする。 だが泰明の静かな声がそれを留めた。符を構えたまま、泰明はあかねを見下ろした。 「神子、何故怨霊を身のうちに留まらせている。何故、封印しない?」 「怨霊?み、神子様に怨霊が取り憑いているのですかっ!」 藤姫がさっと青ざめ、か細い悲鳴を上げる。 「それほど強い怨霊ではない。だが、浄化も封印もせずに身のうちに留めておけば、 龍神の器であるお前の神気は損なわれる。 何故だ、神子。お前ならそのような怨霊、一人で退けることが出来よう。」 脂汗を滲ませながら、あかねはにこっと笑ってみせた。 「・・・・・この怨霊(こ)と約束したんです。力ずくはしないって。 この子が納得できるまで、説得、します。」 あかねの呼吸が乱れている。 少し青ざめたその顔色を見て更に言いつのろうとした藤姫の前に、すっと閉じた蝙蝠が 差し出されて藤姫は目を剥いた。 「友雅殿?」 相変わらず案内の女房など無しで上がり込んだ友雅はこの邸の主には目もくれない。 鋭い目つきでじっと恋人を見つめ、静かに口を開いた。 「・・・・どういうことなのか、説明して貰えるかい?」 |
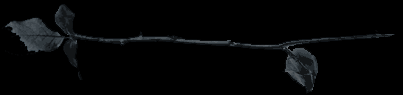
| 夢 見たい / koko 様 |